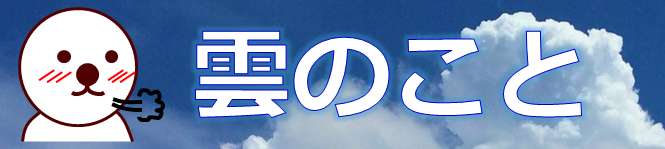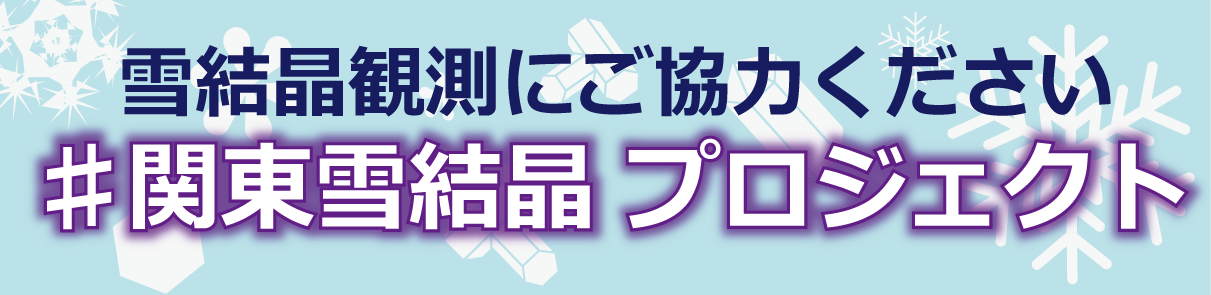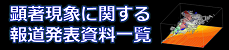令和6年度国立極地研究所・研究集会
|
|
雲凝結核や氷晶核として働くエアロゾルの増減によって雲の構造が変化することにより、降雨や降雪に至る降水機構にも変化が生じる。そのプロセスの理解には、極域を含むエアロゾル・雲・降水に関する知見が必要であり、これまで多くの研究がなされているが、定量的な理解には至っていない。本研究集会では、エアロゾル、雲物理、気象、気候や隣接分野などを専門とする研究者が一堂に集まり、室内実験・観測・数値実験など様々な手法による、エアロゾル・雲・降水に関する最新の研究結果や動向の共有を行う。
|
集合写真
プログラム
発表時間の大まかな目安
口頭発表:1人25〜30分程度(発表:約15〜20分,質疑応答:約10分)
ポスター発表:1日目と2日目に40分ずつ
1日目:2024年2月17日
13:00〜14:50
- 趣旨説明 佐藤 陽祐(北大)
- 雲の将来変化に関する詳しい解析方法 川合 秀明(気象研)
- 衛星観測と気候モデルを用いたエアロゾルの降雨影響とその放射強制力に関する研究 大槻 光理(東大)
- 夏季西部北太平洋における下層雲の航空機直接観測データ解析 山田 耀(東大)
- X帯およびVHF帯レーダの鉛直観測データを用いた雨滴粒径分布の推定 後藤 悠介(名大)
ポスター発表/休憩(4 0 分)
15:30〜17:30
- WRFによる熊本の豪雨再現と東海大学における線状降水帯の研究 宇井 啓人(東海大)
- 超水滴法を用いた降雨を伴う海洋性雄大積雲の数値実験 木舩 佑真(兵庫県大)
- 超水滴法を用いたPi chamberの数値実験 榎戸 耕太郎(兵庫県大)
- 超水滴法における詳細な融解・凍結過程の実装 大橋 隼知(兵庫県大)
2日目:2024年2月15日
10:00〜12:00
- 【総説】気象雷モデルを用いた数値実験〜現状とその課題、今後の開発について〜 佐藤 陽祐(北大)
- RGBヘキサグラムの開発:孤立積乱雲中の霰の成長プロセス解析への適用 近藤 誠(北大)
- 数値モデルを用いた筋状雲の理想化実験 佐藤 海斗(北大)
- ディスドロメータの測定可能範囲を考慮した粒径・落下速度分布の推定 勝山 祐太(森林総研)
昼食(12:00〜13:00)
ポスター発表(13:00〜13:40)
13:40〜15:10
- 2モーメント雲物理スキームへの観測ベースの雲粒粒径分布の導入効果 三隅 良平(日大)
- 電荷ゾンデ再開発のための固体降水粒子の電荷測定地上試験 原 優里佳(山口大)
- 丘陵地形周辺での雪雲の変化を対象とした粒子ゾンデ観測 高見 和弥(鉄道総研)
休憩(10分程度)
15:20〜17:00
- 温暖化がもたらす北極ダストの増加と氷晶形成への影響 松井 仁志(名大)
- Advancing Dust Emission Simulations through the Integration of Dry-Vegetation and Stone-Cover Effects Kaman Kong(RIKEN)
- 南大洋域において観測された非水溶性エアロゾルの発生起源 吉田 淳(極地研)
- 総合討論
ポスター発表
- 2025年2月4日北海道十勝地方の短時間大雪の解析 荒木 健太郎(気象研)
- ビン雲微物理モデルを用いた二峰性雨滴粒径分布の形成タイプ分類 岡崎 恵(京大)
- 熱帯海洋上における巻雲の観測的研究 鈴木 順子(JAMSTEC)
- 低緯度海洋上の対流雲に対する雲生成チェンバー実験 田尻 拓也(気象研)
- GPM/DPRを用いた雪と霰・雹の識別可能性 辻 泰成(富山大)
- 北極陸域での地表気温上昇に伴う氷晶核粒子数濃度の増加 當房 豊(極地研)
- ホログラフィによる重力沈降水滴の統計解析と可視化 中井 大(京工繊大)
- 寒気の吹き出しに伴う筋状降雪雲の理想実験 濱谷 燿平(兵庫県大)
- 観測データ解析と気象化学シミュレーションによるエアロゾル湿性除去過程の定量化 藤野 梨紗子(慶応大)
- 熱帯域における積乱雲の太陽活動/宇宙線変動への応答について 宮原 ひろ子(武蔵野美大)
お問い合わせ
本研究集会に関するお問い合わせは,
![]() :
: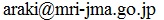 までお願いいたします.
までお願いいたします.
関連情報
- 「2023年度エアロゾル・雲・降水に関する研究集会」2023年2月14〜15日@国立極地研究所
- 「2022年度エアロゾル・雲・降水に関する研究集会」2023年3月16〜17日@国立極地研究所
- 「2021年度エアロゾル・雲・降水の相互作用に関する研究集会」2022年2月21〜22日@国立極地研究所
- 「2020年度エアロゾル・雲・降水の相互作用に関する研究集会」2021年2月16〜17日@国立極地研究所
- 「2019年度エアロゾル・雲・降水の相互作用に関する研究集会」2020年2月17〜18日@国立極地研究所
- 「2018年度エアロゾル・雲・降水の相互作用に関する研究集会」2019年2月14〜15日@国立極地研究所
- 「2017年度エアロゾル・雲・降水の相互作用に関する研究集会」2018年2月14〜15日@国立極地研究所
- 「2016年度エアロゾル・雲・降水の相互作用に関する研究集会」2017年2月16〜17日@国立極地研究所
- 「エアロゾル−雲相互作用について語らう会」2016年2月26日@国立極地研究所

- 雲の微物理過程の研究