



つくばの気象庁機関で毎年行っている「お天気フェアつくば」について、今年度もオンライン開催にて実施させていただきます。
今回は現地での開催と並行した形となりますが、ここでしか見ることのできない、小中学生の皆様にもお楽しみいただけるコンテンツを多数用意いたしましたので、ぜひお楽しみください。
内容がむずかしいコンテンツについては、ぜひおとなの人といっしょに見てください。
※気象研究所ホームページのコンテンツの利用についてはこちらをご覧ください。
暖かくて湿った空気が膨張して、気温が下がると、大気中に含まれる水蒸気が雲粒となって目に見えるようになります。ぬるま湯の入ったペットボトルを急に膨らませて、中の様子を観察しよう。
気象研究所の風洞実験施設には国内で最大級の研究用の気象風洞や回転実験装置があります。これらの装置について紹介します。
気象研究所の低温実験施設にある雲生成チェンバー、-40℃低温室、-90℃低温室について紹介します。(動画あり)
気象研究所で実施している水蒸気観測とその応用について、博士としょう君が紹介します。
オープニング
水蒸気ライダー
気象衛星ひまわり
GNSS、エンディング
全体版
気象研究所の屋上に設置された白いドームの中にある二重偏波レーダー観測装置について説明します。
ディスドロメーター(雨や雪などを測る装置)の観測のしくみや、研究について説明します。
レインスコープ(雨や雪などを撮影する装置)の観測のしくみや、研究について紹介します。
危険な雨雲をすばやく正確にとらえる!最新技術を使った研究をのぞいてみよう。
温暖効果のしくみとその強まりについて、かんたんな実験装置を使って考えてみよう。
日本付近では地震が毎日発生しています。あなたの生まれた日にはどんな地震が発生していたのか調べてみましょう。
地震計のない時代の地震については、昔の人の記録が頼りです。昔の地震について書いてある古文書を読んでみよう。
気象研究所火山研究部で取り組んでいる火山の研究に関連するクイズです。
地球温暖化が進むと日本の気候はどうなっていくのか。どうやって将来の気候を予測するかなどを紹介します。
オゾンホールで有名な観測のしかたについて、二つ紹介します。
お天気にくわしくなろう!気象観測についてのクイズです。
家にある物でパラシュートを作って飛ばしてみよう。大きさ・形・材料を変えるとどうなるかな?
気象庁では、毎日どんな天気でも観測用の気球を飛ばしています。色々な場所・天気で 気球を飛ばすシーンを集めました。
高層気象台で毎日、観測用の気球で空へ飛ばす小さな気象観測器「GPSゾンデ」について、その準備と観測の様子を紹介します。
体に良いところと悪いところがある紫外線。上手に向き合うために紫外線と紫外線対策について学ぼう。
気象測器検定試験センターでは、全国の気象官署で明治以降に使用した約150点の気象測器を気象測器歴史館において展示しています。
展示品には、海外から輸入され、初期の気象観測に用いた晴雨計(気圧計)や温度計、日射計、さらに大正時代に高層気象観測に用いた観測機器など、
他ではなかなか見ることのできない機器が数多く揃っています。 ここでは、この気象測器歴史館について紹介します。
気象庁では、気象官署やアメダスの風の観測精度を維持するため、「風洞」と呼ばれる装置で実際に風を発生させて、定期的に風速計の検査を行っています。また、政府、地方公共団体や、民間企業等が防災等の目的で観測を行う場合にも一定の観測精度を保つため、気象庁の風洞で風速計の精度の検査が行われています。 ここでは、この風洞施設について紹介します。
「未来の天気」は、日本や世界の「今の天気」をもとに、スーパーコンピュータで計算して予測します。そのしくみについて紹介します。
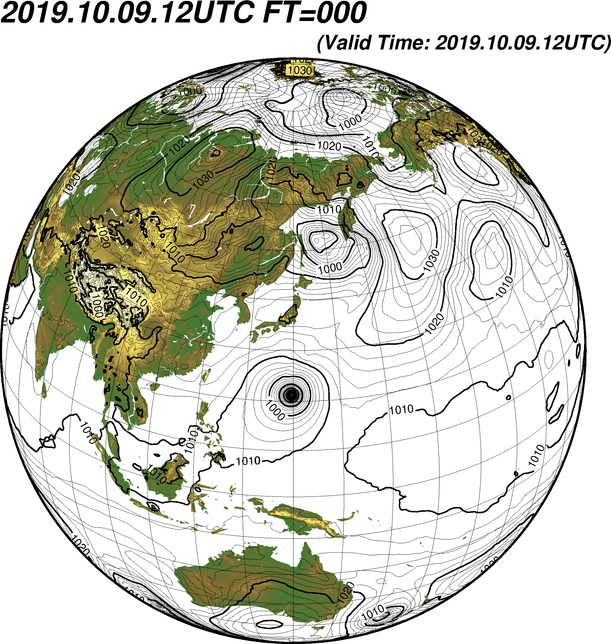
気象研究所の風洞実験施設にある国内最大級の気象風洞や回転実験装置について紹介します。
気象研究所の低温実験施設にある雲生成チェンバー、-40℃低温室、-90℃低温室について紹介します。(動画あり)
気象研究所で実施している水蒸気観測とその応用について、博士としょう君が紹介します。
オープニング
水蒸気ライダー
気象衛星ひまわり
GNSS、エンディング
全体版
気象研究所の屋上に設置された白いドームの中にある二重偏波レーダー観測装置について説明します。
ディスドロメータ(雨や雪などを測る装置)の観測のしくみや、研究について説明します。
レインスコープ(雨や雪などを撮影する装置)の観測のしくみや、研究について紹介します。
危険な雨雲をすばやく正確にとらえる!最新技術を使った研究をのぞいてみよう。
温暖効果のしくみとその強まりについて、かんたんな実験装置を使って考えてみよう。
日本付近では地震が毎日発生しています。あなたの生まれた日にはどんな地震が発生していたのか調べてみましょう。
地震計のない時代の地震については、昔の人の記録が頼りです。昔の地震について書いてある古文書を読んでみよう。
気象研究所火山研究部で取り組んでいる火山の研究についての関連するクイズです。何問正解できるかな?
* 本ファイルを開くには、power point 2003 以上が必要です。画像をクリックするとppsファイル(80MB)がダウンロードされます。
地球温暖化が進むと日本の気候はどうなっていくのか。どうやって将来の気候を予測するかなどを紹介します。
オゾンホールで有名な観測のしかたについて、二つ紹介します。
お天気にくわしくなろう!気象観測についてのクイズです。
家にある物でパラシュートを作って飛ばしてみよう。大きさ・形・材料を変えるとどうなるかな?
気象庁では、毎日どんな天気でも観測用の気球を飛ばしています。色々な場所・天気で 気球を飛ばすシーンを集めました。
体に良いところと悪いところがある紫外線。上手に向き合うために紫外線と紫外線対策について学ぼう。
高層気象台で毎日、観測用の気球で空へ飛ばす小さな気象観測器「GPSゾンデ」について、その準備と観測の様子を紹介します。
気象測器検定試験センターでは、全国の気象官署で明治以降に使用した約150点の
気象測器を気象測器歴史館において展示しています。
展示品には、海外から輸入され、初期の気象観測に用いた晴雨計(気圧計)や温度計、日射計、さらに大正時代に高層気象観測に用いた観測機器など、
他ではなかなか見ることのできない機器が数多く揃っています。 ここでは、この気象測器歴史館について紹介します。
気象庁では、気象官署やアメダスの風の観測精度を維持するため、「風洞」と呼ばれる装置で実際に風を発生させて、定期的に風速計の検査を行っています。また、政府、地方公共団体や、民間企業等が防災等の目的で観測を行う場合にも一定の観測精度を保つため、気象庁の風洞で風速計の精度の検査が行われています。 ここでは、この風洞施設について紹介します。
「未来の天気」は、日本や世界の「今の天気」をもとに、スーパーコンピュータで計算して予測します。そのしくみについて紹介します。
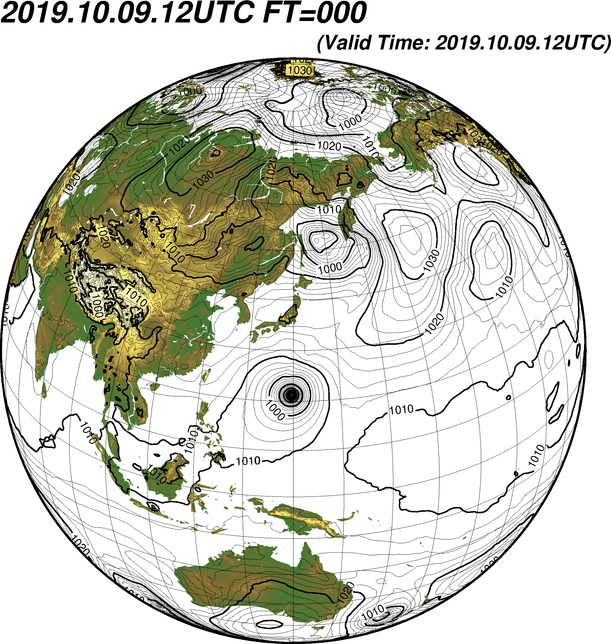
気象研究所のホームページでは、学生の方をはじめ、多くの方に気象研究所の研究について学んでもらうことを目的として、当所で過去に用いられた一般や学生向けコンテンツを掲載しています。
もっとたくさんのコンテンツをご覧になりたい方は、学びのページもご利用ください。
また岐阜地方気象台でお天気教室を開催しております。ぜひこちらもご利用ください。
気象に興味のある方は、地球ウォッチャーズ気象友の会もぜひご覧ください。