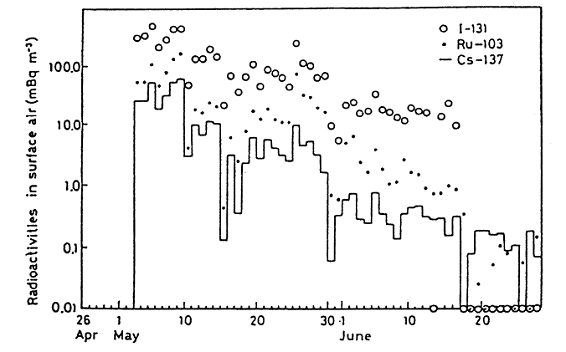|
9.1986年チェルノブイリ原子力発電所事故及び
1997年動燃東海事故由来の放射性核種の輸送 代表的な原子炉事故として、1957年の英国のウィンズケール原子力発電所(Stewart et. al., 1958)、1979年の米国のスリーマイルアイランド原子力発電所及び1986年の旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所を挙げることができる。大気圏核実験とは異なる放射能の大気中への放出過程の中で、規模が最も大きく、しかも詳細な研究が行われたはチェルノブイリ発電所事故である。 1986年4月26日、旧ソ連(現ウクライナ)のチェルノブイリ原子力発電所で深刻な事故が起こり、多量の放射性物質が大気中に放出された。放射性物質の放出は5月5日まで続いた。この間に約1850PBq(50MCi)の希ガスと同量の放射能が放出されたと推定されている。 気象研究所においても、チェルノブイリ原子力発電所由来の放射能の詳細な時間変化及び存在状態を知るための試料採取を行った。また、日本全域での空間的な分布を知るために気象庁の放射能観測網に依頼して、試料採取を行った。放射能測定は、当初迅速に結果をだす目的でガンマ線測定を主に行い、その後90Sr及びPuを測定した。5月3日には、事故現場から約8,000km離れた日本でも初めてチェルノブイリ原子力発電所由来の放射能が観測された。大気中の放射能は急速に増加し137Csでみると、つくばでは5月5日には極大になった。その後、やや放射能が減少した後、5月9日には5月5日とほぼ同じレベルまで大気の放射能は増加した。その後、徐々に減少し、5月25日に第2のピークが見られた後、6月に入ると大気中の放射能レベルは急速に減少した。 日本の5地点(札幌、仙台、東京、大阪、福岡)の地表 大気中の137Cs濃度変化から判断すると、チェルノブイリ原子力発電所由来の放射能は5月3日の時点で日本の北部の北海道及び東北地方に最初に到達し、その後関東、関西及び九州地方にも到達している。5月の137Cs月間降下量は前月に比べ約4桁増加し、観測史上最も高い137Cs月間降下量 を観測した1960年代前半と同程度であった。チェルノブイリ原子力発電所由来の放射能の影響は、日本を含め北半球の中緯度より北側のほとんどの地域に及んだ。 1997年3月11日に動力炉・核燃料開発事業団(動燃)東海事業所「アスファルト固化処理施設」で火災・爆発事故が発生した。その事故により大気中に放出された放射性物質が、水戸、大洗及びつくばで採取した大気浮遊塵の試料から検出された。確認されているのは放射性セシウムのうち137Csが上記3地点で、大洗及びつくばでは134Csも確認されている。気象研究所では、金沢大学低レベル放射能実験施設と協力して、つくばで採取した事故後数日間の大気浮遊塵試料中からも継続して137Csを検出した。このことは、事故により大気中に放出された放射性物質が事故後数日間にわたってつくば周辺に滞留していたことを示している。3月17日以降は、つくばで採取する大気浮遊塵からは放出された放射性物質は検出できなくなった。また、つくば及び東京(千代田区大手町)の降水試料(3月分)の測定を行った結果、137Csは検出されたものの、過去の大気中核実験由来の137Csの値と比較すると変動の範囲内であり、事故由来の放射性セシウムは降水によってはほとんど地表に落下しなかったと思われる。 こうした観測事実から事故由来の放射性物質の挙動を検討するため、数値モデルによるシミュレーションを行った。放出量は1GBqとして計算した。事故により大気中に放出された放射性物質は、事故地点より南から南西の方角に運ばれて、数時間の間に茨城南部、千葉北部、東京東部、埼玉東部に広がった。12日3時頃から東に方向を変え、房総半島を超えていったん太平洋側に流れ出していく。その後12日15時頃から内陸の方向に入りだし、13日早朝にかけて関東平野北部に広がっていく。3月14日には、大気中の137Cs濃度はすでに0.5μBqm-3のレベルに戻っている。数値シミュレーションによると、通過した空気塊の137Cs濃度の最高は約1000μBqm-3である。その後いったん事故以前の濃度まで下がっているが、12日深夜から13日明け方にかけて再び上昇している。3月14日には、大気中の137Cs濃度はすでに0.5μBqm-3のレベルに戻っている。 数値シミュレーション結果と観測値と比較すると、放射能雲が計算領域の外にでてしまったためにつくばでの3月13日10時から3月17日10時までの観測値と計算値には大きな違いがあるが、それを除くとよく一致している。137Csの放出総量の仮定が現実とそう大きくは異なっていないことを意味している。観測値の得られている地点が、関東平野の東に片寄っているので、数値シミュレーションにより得られた濃度のみを、つくばを中心にして東海村を北東の角とする正方形の残りの3つの角にあたる地点について調べた。つくばから南東約60kmの千葉県八日市場市での濃度の変化は、つくばでの変化と基本的には同様であり、最初南から南西に運ばれた影響で12日明け方から濃度が上昇し、約100μBqm-3となっている。その後つくばと同様に、事故以前の濃度まで下がっているが、12日午後から12日深夜にかけて再び上昇している。つくばから北西の栃木県栃木市では12日昼ごろと12日深夜に10-20μBqm-3程度の濃度となっている。つくばから南西の東京都豊島区では、約1μBqm-3程度の濃度上昇が12日に3回見られる。 茅野ら(1977)はSPEEDI高度化モデルをつかい、「低濃度ではあるが分布の端につくばが含まれており、気象研で測定された137Csが事故起因である可能性は高い。」としている。また、彼らの計算によると、つくばへの放射性物質の到着時刻は12日朝5時頃となっており、そのときの濃度は「137Csの放出総量が1GBqという本数値シミュレーションの仮定」を彼等の結果にあてはめると約600-1300μBqm-3となる。つくばへの放射性物質の到着時刻には違いがあるが、定性的には2つの数値シミュレーションの結果は一致している。 〔掲載論文〕(Full texts are not available online, please contact
the authors for reprints.) Igarashi. Y., M. Aoyama, T. Miyao, K. Hirose, K. Komura and M. Yamamoto, Air concentration of radiocaesium in |