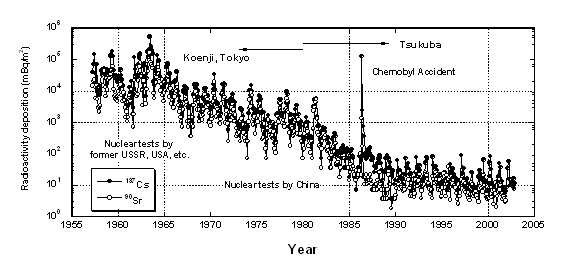|
1.人工放射性降下物(死の灰のゆくえ) 気象研究所では、大気圏での人工放射性核種の濃度変動の実態とその変動要因を明らかにすべく、ビキニ事件からまもなくの1954年4月に放射性降下物(いわゆるフォールアウト)の観測を開始した(当初は全β観測)。月間降水・降下塵中の核種分析は1957年に始まり、以降現在に至るまで40数年間途切れることなく継続されている。特に気象研究所での観測値は、現在でも検出限界以下とすることなく必ず数値化されている。対象は重要な核種である90Sr、137CsおよびPu同位体である。当初は全国5地点の気象官署で試料採取を行ってきたが、次第に観測地点を加えて1979年に現在の北緯24度から45度にまたがる全国12地点での観測となった。放射性降下物は主として大気圏内核実験により全球に放出されたため、部分核実験停止条約の発効前に行われた米ソの大規模実験の影響を受けて1963年の6月に最大の降下量となり(90Sr 約170Bq/㎡、137Cs
約550 Bq/㎡)、その後徐々に低下した。しかし、60年代中期より開始された中国核実験による影響で降下量は度々増大し、1980年を最後に核実験が中止されたので漸くに低下した。1986年4月の旧ソ連チェルノブイリ原子力発電所の事故により、放射能の降下量は再び増大したが、1990年代になり90Sr、137Csの月間降下量はともに数~数10mBq/㎡で推移しており、「放射性降下物」とは呼べない状況に至った。この40数年間に亙る時系列データは、ハワイマウナロアにおける二酸化炭素の時系列データ同様、地球環境に人工的に汚染物質を付加した場合、汚染物質がどのような環境動態をとるのかを如実に反映しており、実に5桁の降下量の水準変動が記録されている。 初期の一連の研究により、重要な気象学的知見が得られた。例えば、降下量の時間変動から対流圏、成層圏における放射性物質の滞留時間がそれぞれ、30~50日、1.0~1.2年と求められた。これは翻って粒子状物質(エアロゾル)の滞留時間を求めたことにほかならない。また、放射能の降下量は太平洋側では春に増大し、日本海側では冬に増大すること、北半球で考えると中緯度地帯に降下量の極大があり、成層圏―対流圏の大気交換過程に主たる原因があることなどが明らかにされた。これらは成層圏エアロゾルの地表面への沈着について科学的示唆を与えるものである。このほか、核実験では半減期約53日の89Srも放出されることから、89Sr/ 90Sr放射能比を用いて各回の中国核実験による降下量の寄与分が見積もられた。その結果、各実験の寄与の季節変化が明らかとなったが、その核実験が実施された季節の違いと実験の規模により放射能の打ちこまれる高度が変わることが原因となって、季節変化のパターンが違うことがわかった。 この放射能の降下量の季節変化と経年の変動をより定量的に説明するために、従来からの大気輸送ボックスモデルを改良して北半球4ボックスモデルによる解析が行われた。上部成層圏、下部成層圏、対流圏に加えて、対流圏界面付近の混合層を置き、一次の速度式に従って放射能が輸送されると仮定し、上部から滞留半減期をそれぞれ0.5、0.7および0.3年とした場合、観測結果をよく再現できた。また、このモデルにより核実験による放射能の成層圏への打ち上げ量を評価できた。 1990年代になると、90Sr、137Cs、Puの降下量は大きく低下し、試料採取に4㎡の大型水盤を用いている気象研究所以外では検出限界以下となって、降下量を容易に数値化できなくなった。このため、気象研での観測記録は我が国のみならず世界で唯一最長の記録となっている。チェルノブイリ事故由来放射能の一部は下部成層圏にも輸送されたが、1994年以後の年間降下量は成層圏滞留時間から予想される量を大きく上回り、むしろほぼ一定量で推移する状況(変動幅2倍程度)となった。従って、成層圏以外のリザーバーから放射能が供給されており、それは表土と考えられる。一旦地表面に沈着した放射能は、風によって土壌粒子とともに大気中に浮遊する。この過程が再浮遊であり、大気への放射能の供給源として重要となってきた。再浮遊は、従来、近傍の畑地などからの表土粒子が主体となっていると信じられてきた。しかしながら、降下物の137Cs/90Sr放射能比は、気象研近傍で採取した表土中の同比と値が一致せず、再浮遊には複数の起源のあることが明らかとなった。他の起源として想定できる地球化学的な現象としては、表土粒子が大規模に輸送される風送塵(黄砂)がある。そこで、この仮説を検証するための取り組みを開始した。最初の試みとして、大陸の砂漠域で90年代に採取された表土につき測定を行い、つくばの土壌と比較したところ、137Cs濃度はほぼ同水準であるが、90Sr濃度はつくば土壌の数倍で、核実験で降下した放射能が降水によって溶出されることなく、残留している様子が示された。また、137Cs/90Sr放射能比は降下物試料での同比に近く、比を利用した2成分混合の計算からも風送塵(黄砂)が放射能輸送に寄与していることが強く示唆された。風送塵に関する研究は、近年の気候変動研究にも対応し、科学的新知見を与え得るものである。人工放射能をトレーサーとして風送塵の研究に応用できる可能性が見えつつある。このように、環境研究においては時系列データが如何に貴重なものであるか再度強調したい。 〔掲載論文〕(Full texts are not available online, please
contact the authors for reprints.) Hirose,
K., Y. Igarashi, M. Aoyama, T. Miyao, Long-term trends of plutonium fallout
observed in Igarashi,
Y., M. Aoyama, K. Hirose, T. Miyao, |